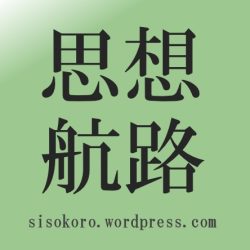ウクライナの歴史と言ってもそんなに簡単にまとめられないことはわかっていたが、とりあえずブログに書いてみようと思って始めてしまったシリーズ第2弾。
ウクライナの歴史の詳細を読めば読むほどに複雑で理解することすら難しく、これを知っているからと言って何の役に立つのかわからなくなってくる感じもあるが、国際的な関係性から見たウクライナの立ち位置がなんとなくわかってくる、気がする。
リトアニアとポーランドによる支配の時代
14世紀半ばにハーリチ・ヴォルイニ公国が滅びて以降300年間はリトアニアとポーランドがウクライナの地を支配した。
13世紀中頃ミンダウガス公に統一されたリトアニアは東部と南部へ進出してハーリチのダニーロと対峙した。
この東・南進政策ほ14世紀初めにゲディミナスによって受け継がれベラルーシの大部分とウクライナ北部を治めた。
ゲディミナスの死後もリトアニアはその勢力を拡大して、1362年には不敗を誇ったキプチャク汗国と戦いヨーロッパで最初に勝利し、ウクライナ中部も征服してハーリチ地方を除くほぼ全てのウクライナとベラルーシを支配下にした。
リトアニア人は「古いものは壊さず、新しいものは持ち込まず」という方針で臨みその土地のルーシ系貴族を登用したため彼らから歓迎された。
一方、ポーランドは13世紀に神聖ローマ帝国やドイツ騎士団から領土を削り取られ、出口として東側へ進出することになる。
カジミエシ3世は衰退しつつあるハーリチ・ヴォルイニ公国に目をつけて皇位継承に干渉し同国に食い込もうとしているリトアニアとも争った。
こうして14世紀中頃にはハーリチ地方はポーランドの領有下に入った。
宗教的にキーウ・ルーシが東方キリスト教(正教)だったのに対しポーランドは西方キリスト教(カトリック)だったこともありポーランドはリトアニアと違って自分たちの文化を押し付けていった。
このためポーランドのウクライナ進出はスムーズに進まなかったが最終的に大きな影響をあたえたのはポーランドのほうだった。
ポーランド支配下のウクライナでおきたことの特徴は、ポーランド人の領主に対してウクライナの地に住む民が農奴化していったことで農民たちは厳しく税を取り立てられ貴族はその搾取により栄えていった。
コサックは日本で言うサムライ?
コサック、と言われるとコサックダンスを思い浮かべるのは俺だけだろうか、しゃがんだ姿勢から足を伸ばしたり引っ込めたり、かなり膝や腰への負担が大きそうなダンスだ。
その動きがイコール、コサックダンスということでもないのだろうがそれしか思い浮かばない…。
では、コサックとは何なのか?
15世紀ころからロシア南部やウクライナのステップ地帯に住みついた民によって出自を問わない自治的な武装集団が作り上げられれ、その構成員たちがコサックと呼ばれた。
16世紀までにコサックはさらに武力をつけると、当初はタタール人から辺境の地を守っていたのが逆にタタール人を襲うようになる。
やがてコサックが住むコサックの町ができて16世紀末にはその町は王に任命された「ヘトマン」によって率いられるようになり、コサック町では満足できないドニエプル下流に住む者たちは「シーチ」と呼ばれる塞化した拠点を作った。
この地は「ザポロージェ・シーチ」と呼ばれるようになりコサックの中心地となっていった。
コサックは死を恐れずに戦い、自由を愛していた、とのこと。
その生き様への共感が今もなおウクライナ人のアイデンティティとしてコサックの存在が語り継がれる理由のひとつと思われるが、日本人の中にサムライの生き様を日本人のアイデンティティとして誇る人がいることと似ているのかもしれない。
ハサイダチニー、フメリニッキー、マゼッパなどがヘトマンとして名前を残した。
特にフメリニッキーは1650年頃に実質的な独立国家として初のウクライナ国家を築いたヘトマンとして英雄とされている人物だが、一方で彼がモスクワと結んだ保護条約がウクライナがロシアに併合されるきっかけを作ったとして非難する者もいる。
小領主の家に生まれ父がフメリニッキーの反乱に加わったことのある人物であり、その息子でヘトマンとなったマゼッパはモスクワのツァーリの庇護のもと平和な状況下でウクライナの自治の拡大を思い描いていたがモスクワはいつかウクライナの影響を排除して自分達が直接的に統治しようと考えていた。
モスクワとの軋轢は次第に大きくなり、1709年にマゼッパ率いるスェーデンとコサックの連合軍とピョートルが率いるモスクワ軍がウクライナ中部のポルタヴァで激突する。
その結果はモスクワ軍の大勝だった。
マゼッパはコサックたちと共に亡命するがベッサラビアで力尽き、これ以降コサックによるヘトマン国家は衰退し続けていく。
1775年にロシアのエカテリーナ2世はトルコとの戦争で得た黒海沿岸地域を一括して新ロシア県を創設し植民政策をとった。
1783年にはコサックの連隊制度を廃止してロシア軍に編入しウクライナはロシア帝国の一地方となり、ヘトマン国家はここで消滅することになる。
ロシア帝国下でウクライナは「小ロシア」と呼ばれていた
18世紀の末から第一次世界大戦までの120年間はウクライナの土地の約八割がロシア帝国に残り二割がオーストリア帝国に支配される。
ロシア帝国化ではウクライナは行政上の名前で「小ロシア」と呼ばれていた。
ドニエプル川の左岸では農民の移動の自由が禁止されて完全に農奴化し、右岸でもポーランドの支配下ですでに農奴は存在していて19世紀半ばには3/4が農奴となっていた。
右岸地方は行政的にはロシアの支配下にあったがロシア人はほとんど住んでおらずポーランド人領主が土地を所有していた。
ウクライナの都市の住民は大部分がロシア人とユダヤ人で都市に住むウクライナ人は少なかったが彼らはロシア語を話すようになりロシア人化していった。
これに対して農村では圧倒的多数のウクライナ人が頑なにウクライナ語と固有の習慣を守っており、都市と農村では別の国のようであった。

ロシアにおいては政府も左派もウクライナの自主性を認めようとせず1876年にウクライナ語の使用制限、結社の自由の制限が撤廃されたにも関わらず保守化した議会の影響によってウクライナ系の多くの団体や出版物は姿を消した。
一方でオーストリア帝国下ではウクライナ民族を主要民族に同化させるような圧力はなく地域は狭いながらウクライナナショナリズムの拠点となっていき、西部地域は現在に至るまでロシアの影響が薄い地域となる。
ハーリチナではウクライナ人の民族覚醒の動きは着実に進み1860〜1870年代にかけて民族主義的な多くの組織が結成され、1894年にはリヴィウ大学にウクライナ研究の講座がはじめて設けられるなどオーストリアの比較的自由な雰囲気のもとでハーリチナなどがウクライナ民族主義の中心となった。
ロシア帝国支配下のウクライナでは植民地状態であるにも関わらず作家のゴーゴリやトルストイ、ノーベル賞を受賞した細菌学者のイリア・メチニコフなど世界に名を残すような芸術家や学者が多く輩出された。
正直、もう書くのが疲れてきたがまだウクライナの歴史は続く、ただ、俺が書き疲れたのでもしかしたら第3弾はないかもしれない、気が向いたら書くかも…。