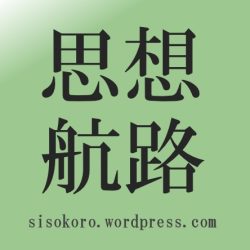去年の夏頃に芥川龍之介の「蜘蛛の糸」を読んだ。
コロナ騒動が始まって程なくして「この騒ぎなんかおかしくない?」と思い始めてから感染症や免疫に関する本や、ワクチンが始まる頃からはワクチンに関する本も読みあさっていてたのだが、さすがに飽きてきて違う感じの本もたまには読みたいと思って選んだのが「蜘蛛の糸」だった。
なぜ蜘蛛の糸なのかと言うと、小林よしのりの漫画の中のセリフで「日本でも我先にとワクチンを求める亡者があとを絶たないが芥川龍之介の蜘蛛の糸のように切れてしまわなければいいのだが…」というものがあり、地獄から罪人が登ってきた蜘蛛の糸はプツッと切れて糸につかまっていた人達は全員また地獄に落ちてしまうわけだけど、そう言えば「蜘蛛の糸」ってどんな話だったのか細かいところをまったく覚えていない、ということでAmazonをポチッとして芥川龍之介の「蜘蛛の糸」を文庫本で取り寄せてみた。
主人公の犍蛇多(かんだた)は生前、人殺しや盗みをはたらいて地獄に落ちた人だが、ある日踏み殺そうとした蜘蛛を、いや待て殺してしまっては可哀想だと助けてあげたということで善いこともしたのだからお釈迦様が地獄から助けてあげようと犍蛇多のもとへ蜘蛛の糸を垂らすわけです。
これ、読んでいて思ったけど蜘蛛を踏み潰そうとしてやめたことは特に善いことをしたというわけでもなんでもなく、ただその時の気分で踏むのをやめただけのことでしかない。
でも、物語は淡々と語られていく。
整合性の取れない矛盾のようなものを抱えたまま淡々と語られる感じにこの話の壮大な世界観を感じてしまった。
犍蛇多が登っている途中に蜘蛛の糸に数限りない罪人たちが後を追いかけて登ってくるのに気付いて、こら下りろ、とわめいたところで蜘蛛の糸は切れてしまうわけだがそれを見ていたお釈迦様は悲しそうな顔をしてまたぶらぶら歩き始めるだけ。
そして極め付けは「極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません」の描写。
何も起きていなかったかのように極楽の日常はまた続いていくわけだが、この世の中の不条理をまざまざと見せつけられているような感覚になる。
にもかかわらず、なぜか芥川龍之介の文章は心地よいというか自然に体に入ってくるのが不思議なところで、文字を追いかけていると語られている情景が色鮮やかに浮かんできて癒される。
杜子春やトロッコなどの短編も収録されているが、どれを読んでも子供の頃読んでもらった絵本のような懐かしい感じと鮮やかな情景が浮かんでその世界観に引き込まれる。
小学校の国語の授業で読んだ時にはわからなかったが、大人になっていろいろなことがわかってきたからこそ読んでみて価値のある物語だとも言える。
芥川龍之介は太平洋戦争が始まる少し前に自殺している。
ぼんやりとした不安を感じていたようだが、それが戦争に対する不安なのか自身の将来に対するものなのかはよくわからない。
芥川龍之介の文章は心に潤いをもたらす効果抜群、おすすめしたい。